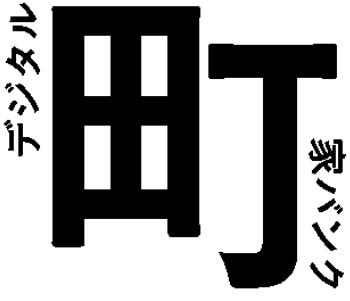「親が所有していた京町家を相続することになったけど、どうすれば良いのか分からない」「相続税の負担が心配」「遠方に住んでいるので、管理できない」——京町家を相続された方の中には、このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
京町家は、京都の歴史と文化を体現する貴重な文化的資産である一方、相続税の負担、維持管理の手間、修繕費用の問題など、相続に伴う様々な課題があります。
本記事では、京町家を相続した際に知っておくべき税金、維持費、そして取るべき3つの選択肢について、詳しく解説します。
京町家の相続で直面する5つの問題
京町家を相続すると、以下のような問題に直面することがあります。
問題1:相続税の負担が大きい
京町家は、京都市中心部に位置することが多く、土地の評価額が高いため、相続税の負担が大きくなることがあります。
特に、複数の相続人がいる場合、相続税を支払うために京町家を売却せざるを得ないケースもあります。
問題2:維持管理の手間とコストがかかる
京町家は、伝統的な木造軸組工法で建てられており、定期的なメンテナンスが必要です。特に、屋根の葺き替え、外壁の修繕、白蟻対策などには、多額の費用がかかります。
また、遠方に住んでいる場合、定期的に京都に通って管理することが難しく、管理会社に委託する必要があります。これにも費用がかかります。
問題3:修繕費用が高額になる
京町家は築年数が古いため、相続時にはすでに老朽化が進んでいることが多いです。雨漏り、床の傾き、柱の腐食など、様々な問題が発生しており、修繕には数百万円から1,000万円以上かかることもあります。
問題4:相続人間での意見の相違
複数の相続人がいる場合、京町家をどうするかについて意見が分かれることがあります。
- 「京町家を残したい」という相続人
- 「売却して現金化したい」という相続人
- 「賃貸に出して収益を得たい」という相続人
このような意見の相違が、相続人間のトラブルに発展することもあります。
問題5:相続放棄しても管理義務が残る
「京町家の維持管理が負担なので、相続放棄したい」と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、2023年の民法改正により、相続放棄をしても、「現に占有している」者は、次の相続人が管理を始めるまで管理義務を負うことになりました。
つまり、相続放棄をしても、すぐに管理義務から解放されるわけではないのです。
京町家の相続にかかる税金
京町家を相続する際には、以下の税金がかかります。
1. 相続税
相続税は、相続財産の総額が基礎控除額を超える場合に課税されます。
基礎控除額の計算式:
- 基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
例えば、法定相続人が3人の場合:
- 基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円
相続財産の総額が4,800万円を超える場合、超えた部分に対して相続税が課税されます。
相続税の税率:
| 課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | – |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
2. 登録免許税
相続登記(不動産の名義変更)を行う際には、登録免許税がかかります。
税率:
- 固定資産税評価額 × 0.4%
例えば、固定資産税評価額が2,000万円の場合:
- 登録免許税 = 2,000万円 × 0.4% = 8万円
3. 固定資産税・都市計画税
京町家を相続した後、所有し続ける場合は、毎年、固定資産税と都市計画税がかかります。
固定資産税:
- 固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率)
都市計画税(市街化区域内の場合):
- 固定資産税評価額 × 0.3%(京都市の場合)
例えば、固定資産税評価額が2,000万円の場合:
- 固定資産税 = 2,000万円 × 1.4% = 28万円
- 都市計画税 = 2,000万円 × 0.3% = 6万円
- 合計 = 34万円
ただし、住宅用地の特例が適用される場合、税額が軽減されます。
4. 非居住住宅利活用促進税(空き家税)
2029年度から、京都市の市街化区域内にある空き家に対して、「非居住住宅利活用促進税」(通称:空き家税)が課税されます。
詳細は、京都市の空き家売却で後悔しないための完全マニュアルをご参照ください。

京町家の維持管理にかかる費用
京町家を相続した後、所有し続ける場合は、以下のような維持管理費用がかかります。
1. 定期的なメンテナンス費用
京町家は、伝統的な木造軸組工法で建てられており、定期的なメンテナンスが必要です。
| 項目 | 頻度 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 屋根の葺き替え | 20〜30年に1回 | 200万円〜500万円 |
| 外壁の修繕 | 10〜15年に1回 | 100万円〜300万円 |
| 白蟻対策 | 5年に1回 | 10万円〜30万円 |
| 畳の張り替え | 10〜15年に1回 | 1畳あたり1万円〜3万円 |
| 建具の修繕 | 必要に応じて | 1箇所あたり5万円〜20万円 |
2. 管理会社への委託費用(遠方に住んでいる場合)
遠方に住んでいる場合、管理会社に委託する必要があります。
費用の目安:
- 月額1万円〜3万円程度
3. 光熱費(空き家の場合でも最低限の契約が必要)
空き家の場合でも、定期的な換気や清掃のため、最低限の電気・水道の契約が必要です。
費用の目安:
- 月額5,000円〜1万円程度
4. 火災保険料
京町家は木造建築のため、火災保険料が高額になることがあります。
費用の目安:
- 年額5万円〜15万円程度
京町家を相続したら取るべき3つの選択肢
京町家を相続した場合、以下の3つの選択肢があります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、ご自身の状況に最適な選択をしましょう。
選択肢1:自分や家族が住む
京町家に愛着があり、京都での生活を希望する場合は、自分や家族が住むという選択肢があります。
メリット:
- 京町家を後世に残すことができる
- 京都の伝統的な暮らしを体験できる
- 相続税の「小規模宅地等の特例」を利用できる可能性がある
- 固定資産税の住宅用地特例が適用される
デメリット:
- 維持管理の手間とコストがかかる
- 修繕費用が高額になる可能性がある
- 現代的な生活設備が不足している場合、リフォームが必要
こんな方におすすめ:
- 京町家に愛着があり、後世に残したい
- 京都での生活を希望している
- 維持管理の手間とコストを負担できる
注意点:
- 相続後、すぐに住み始めない場合、空き家税の対象となる可能性がある
- 修繕が必要な場合、京都市の補助金制度を活用できるか確認する
選択肢2:賃貸に出して収益を得る
京町家を賃貸に出すことで、家賃収入を得ながら、京町家を保全することができます。
メリット:
- 家賃収入を得られる
- 京町家を後世に残すことができる
- 維持管理を借主に任せることができる(契約内容による)
- 固定資産税の住宅用地特例が適用される
デメリット:
- 賃貸に出す前に、リフォームが必要な場合がある
- 借主が見つからない場合、空室リスクがある
- 借主とのトラブルが発生する可能性がある
- 賃貸収入に対して所得税がかかる
こんな方におすすめ:
- 京町家を残したいが、自分では住まない
- 家賃収入を得たい
- 賃貸経営に興味がある
活用方法の例:
- 一般的な居住用賃貸:家族やカップル向けに賃貸
- ゲストハウス:観光客向けの宿泊施設として運営
- シェアハウス:複数の入居者でシェアする形式
- 事業用賃貸:カフェ、ギャラリー、オフィスなどとして賃貸
注意点:
- 京町家をゲストハウスとして運営する場合、旅館業法の許可が必要
- 賃貸に出す前に、京都市の補助金制度を活用してリフォームすることを検討する
選択肢3:売却して現金化する
京町家の維持管理が難しい場合、売却して現金化するという選択肢があります。
メリット:
- 維持管理の手間とコストから解放される
- まとまった現金を得られる
- 相続税の支払いに充てることができる
- 相続人間で現金を分割しやすい
- 「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」を利用できる可能性がある
デメリット:
- 京町家を手放すことになる
- 売却価格が期待よりも低い場合がある
- 売却に時間がかかる場合がある
こんな方におすすめ:
- 遠方に住んでおり、管理が難しい
- 維持管理の手間とコストを負担できない
- 相続税の支払いのため、現金が必要
- 相続人間で現金を分割したい
注意点:
- 「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」の適用要件を確認する
- 京町家の専門知識を持つ不動産会社に相談する
- 複数の不動産会社に査定を依頼し、適正価格を把握する

京町家の相続税を軽減する方法
京町家の相続税を軽減するためには、以下のような方法があります。
方法1:小規模宅地等の特例を利用する
被相続人(亡くなった方)が居住していた宅地を相続する場合、一定の要件を満たせば、土地の評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」を利用できます。
主な要件:
- 被相続人が居住していた宅地であること
- 相続人が配偶者、または同居していた親族であること
- 相続後も引き続き居住し、所有し続けること
減額の上限:
- 居住用宅地:330㎡まで、評価額を80%減額
例:
- 土地の評価額:5,000万円
- 特例適用後:5,000万円 × (1 – 80%) = 1,000万円
このように、特例を利用することで、相続税を大幅に軽減できます。
方法2:相続前にリフォームして評価額を下げる
建物の評価額は、固定資産税評価額をもとに計算されます。相続前にリフォームを行うことで、建物の評価額を下げることができる場合があります。
ただし、この方法は専門的な知識が必要なため、税理士に相談することをおすすめします。
方法3:生前贈与を活用する
被相続人が生前に、少しずつ財産を贈与することで、相続財産を減らし、相続税を軽減できます。
暦年贈与:
- 年間110万円までの贈与は非課税
相続時精算課税制度:
- 2,500万円までの贈与は非課税(ただし、相続時に精算される)
京町家の相続で失敗しないための3つのポイント
ポイント1:早めに専門家に相談する
京町家の相続は、税金、法律、不動産など、様々な専門知識が必要です。早めに、税理士、弁護士、不動産会社などの専門家に相談しましょう。
相談すべき専門家:
- 税理士:相続税の計算、節税対策
- 弁護士:相続人間のトラブル、遺産分割協議
- 不動産会社:京町家の査定、売却方法の提案
- 司法書士:相続登記の手続き
ポイント2:相続人間でしっかり話し合う
複数の相続人がいる場合、京町家をどうするかについて、早めに話し合いましょう。意見の相違が大きい場合は、弁護士に相談し、遺産分割協議を進めることをおすすめします。
ポイント3:京都市の補助金制度を活用する
京都市では、京町家の保全と活用を促進するため、様々な補助金制度を設けています。これらを活用することで、修繕費用を抑えたり、賃貸に出す際のリフォーム費用を補助してもらったりすることができます。
主な補助金制度:
- 京町家等継承ネット事業:京町家の改修費用の一部を補助
- 木造住宅耐震改修助成事業:木造住宅の耐震改修費用の一部を補助
- 建物活用補助:空き家を売却した際の仲介手数料を補助
詳細は、京都市の担当窓口に問い合わせてください。
京町家の相続放棄は慎重に検討する
「京町家の維持管理が負担なので、相続放棄したい」と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、相続放棄には以下のような注意点があります。
注意点1:すべての相続財産を放棄することになる
相続放棄をすると、京町家だけでなく、すべての相続財産を放棄することになります。預貯金、株式、その他の不動産など、プラスの財産も受け取ることができなくなります。
注意点2:管理義務が残る場合がある
2023年の民法改正により、相続放棄をしても、「現に占有している」者は、次の相続人が管理を始めるまで管理義務を負うことになりました。
つまり、相続放棄をしても、すぐに管理義務から解放されるわけではないのです。
注意点3:次の相続人に負担が移る
相続放棄をすると、次の法定相続人に相続権が移ります。例えば、子が相続放棄をすると、親(被相続人の親)に相続権が移ります。
これにより、次の相続人に負担が移ることになるため、事前に相談することが重要です。
相続放棄よりも売却を検討する
相続放棄を検討している方は、まず売却を検討することをおすすめします。京町家は、専門知識を持つ不動産会社に相談することで、思わぬ高値で売却できることがあります。
売却することで、維持管理の負担から解放され、現金を得ることができます。
まとめ:京町家の相続は早めの対応が重要
京町家の相続は、税金、維持費、相続人間の調整など、様々な課題があります。しかし、早めに専門家に相談し、適切な対応を取ることで、これらの課題を解決することができます。
京町家を相続された方は、まず以下のステップを踏むことをおすすめします。
- 税理士に相談して、相続税の試算を行う
- 相続人間で話し合い、京町家をどうするか方針を決める
- 京町家の専門知識を持つ不動産会社に相談し、査定を受ける
- 京都市の補助金制度を確認し、活用できるものがないか調べる
- 「自分や家族が住む」「賃貸に出す」「売却する」の3つの選択肢から、最適なものを選ぶ
京町家は、京都の歴史と文化を体現する貴重な文化的資産です。適切な対応を取ることで、京町家を後世に残すことも、現金化して新たな人生のスタートを切ることもできます。
この記事に関連するおすすめ記事:
- 京都市の空き家売却で後悔しないための完全マニュアル|税金・費用・手続きを解説
- もう迷わない!京町家売却で本当に信頼できる不動産会社の選び方【5つのチェックリスト】
- その古い家、実は「京町家」かも?見分け方と売却時の3つの注意点
参考文献:
- 株式会社光徳「京町家相続問題 売却がもたらす解決策とは?」https://furuya-kaitori.com/column/20230813/kyoumachiya-souzoku
- ケのハレ「町家相続問題、手放す?それとも活用する?所有者向けガイド」https://www.kenohare.com/souzoku-machiya/
- 京都市「京町家を取り巻く現状」https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/cmsfiles/contents/0000244/244042/4_genjo.pdf
- NPO法人 京都町並み保存協議会「空家・相続問題を解決」https://kyoto-akiya.or.jp/