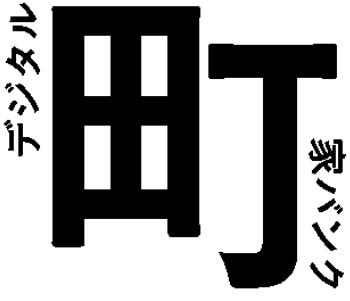京都市内で不動産の売却を検討されている方にとって、「今が売り時なのか」「どのように進めればいいのか」「どのくらいの価格で売れるのか」といった疑問は尽きないものです。
本記事では、2025年最新の京都市の不動産売却相場から、売却の流れ、注意すべきポイントまでを網羅的に解説します。
京都市の不動産売却相場(2025年最新版)
一戸建ての売却相場
京都市内の一戸建て売却相場は、2023年以降、安定した推移を見せています。
京都不動産買取相談センターの調査によると、2024年の平均買取価格は2,736万円、平均仲介価格は3,219万円となっており、前年比でわずかに上昇しています。
| 年 | 平均買取価格 | 平均仲介価格 |
| 2023年 | 2,649万円 | 3,117万円 |
| 2024年 | 2,736万円 | 3,219万円 |
この数字から分かるように、京都市の一戸建て市場は大きな値崩れもなく、堅調な需要が続いています。
特に、若者世帯や子育て世帯からの需要が底堅く、駅徒歩12分圏内、築30年前後の物件が中心に取引されています。
エリア別の中古一戸建て相場
京都市内でも、エリアによって相場は大きく異なります。以下は主要エリアの平均相場です。
| エリア | 平均相場 |
| 京都市左京区 | 3,250万円 |
| 京都市北区 | 2,680万円 |
| 京都市伏見区 | 1,980万円 |
| 京都市右京区 | 1,980万円 |
左京区や北区といった、京都市中心部や大学が多いエリアは高値で推移している一方、伏見区や右京区は比較的手頃な価格帯となっています。
ただし、これらのエリアも滋賀県や大阪府へのアクセスが良く、ベッドタウンとして根強い人気があります。
マンションの売却相場
京都市のマンション売却相場は、2025年9月時点で平均3,515万円(坪単価166万円)となっています。
特に中京区の中古マンション(3LDK・70平米)は約4,269万円と、過去最高水準で推移しています。上京区や下京区も同様に高値を維持しており、マンション市場は活況を呈しています。
土地の売却相場
京都府全体の土地売却価格は、2025年9月時点で平均2,600万円です。京都市内の土地は、観光地や歴史的景観地区の規制、再建築不可物件の存在など、特有の条件が価格に影響を与えることがあります。
2025年の市場予測
京都市の不動産市場は、2015年から2024年にかけて上昇傾向にありましたが、2025年以降は大きな開発計画がないことから、価格は横ばいで推移すると予測されています。
ただし、若者世帯・子育て世帯からの一戸建て需要は引き続き底堅く、売却しやすい環境は続くと見込まれます。
不動産売却の流れ(7ステップ)
不動産売却は、準備から引き渡しまで、一般的に3ヶ月〜6ヶ月程度の期間を要します。
以下、7つのステップに分けて解説します。
ステップ1:売却の準備と相場調査
まずは、ご自身の不動産がどのくらいの価格で売れるのか、相場を調べることから始めます。
インターネットの不動産ポータルサイト(SUUMO、HOME’Sなど)で、同じエリア・同じ条件の物件がいくらで売り出されているかを確認しましょう。
また、この段階で売却の目的を明確にすることも重要です。
「できるだけ早く現金化したい」のか、「時間がかかっても高く売りたい」のかによって、選ぶべき売却方法(仲介か買取か)が変わってきます。
ステップ2:不動産会社に査定を依頼
相場感を掴んだら、次は不動産会社に正式な査定を依頼します。査定には、簡易査定(机上査定) と 訪問査定 の2種類があります。
簡易査定は、物件の情報(立地、築年数、面積など)をもとに、過去の取引事例から概算価格を算出する方法です。一方、訪問査定は、実際に不動産会社の担当者が物件を訪問し、建物の状態や周辺環境を確認した上で、より正確な査定額を提示します。
ポイント: 査定は必ず複数の不動産会社に依頼しましょう。
会社によって査定額に差が出ることがあり、比較することで適正価格を見極めることができます。
ステップ3:不動産会社と媒介契約を結ぶ
査定結果を比較し、信頼できる不動産会社を選んだら、媒介契約を結びます。媒介契約には、以下の3種類があります。
| 契約の種類 | 複数社との契約 | 自己発見取引 | レインズ登録 | 報告義務 |
| 一般媒介契約 | 可能 | 可能 | 任意 | なし |
| 専任媒介契約 | 不可 | 可能 | 義務(7日以内) | 2週間に1回以上 |
| 専属専任媒介契約 | 不可 | 不可 | 義務(5日以内) | 1週間に1回以上 |
一般媒介契約は複数の不動産会社に同時に依頼できる自由度の高い契約ですが、不動産会社側の積極性が低くなる可能性があります。
一方、専任媒介契約や専属専任媒介契約は、1社に絞る代わりに、不動産会社が積極的に販売活動を行い、定期的な報告も受けられます。
ステップ4:売却活動の開始
媒介契約を結ぶと、不動産会社が売却活動を開始します。
具体的には、不動産ポータルサイトへの掲載、チラシの配布、オープンハウスの開催などが行われます。また、不動産会社専用のネットワーク「レインズ(REINS)」に物件情報が登録され、全国の不動産会社が買主を探すことができるようになります。
この期間中、購入希望者が内覧に訪れることがあります。第一印象が重要ですので、事前に清掃や整理整頓を行い、明るく清潔な状態を保つよう心がけましょう。
ステップ5:買主と売買契約を締結
購入希望者が現れ、価格や条件について合意に至ったら、売買契約を締結します。契約時には、以下の書類や手続きが必要です。
•売買契約書の作成・署名・押印
•手付金の受領(通常、売却価格の5〜10%)
•印紙税の納付(売買契約書に貼付)
契約後、買主は住宅ローンの本審査を受けます。この審査に通過すると、決済・引き渡しの日程が確定します。
ステップ6:決済と引き渡し
売買契約から約1ヶ月後、決済と引き渡しが行われます。決済日には、買主から残代金が支払われ、同時に物件の所有権が移転します。この手続きは、通常、司法書士が立ち会いのもと、金融機関で行われます。
決済日に必要なもの:
•登記済権利証(または登記識別情報)
•実印と印鑑証明書
•固定資産税納税通知書
•本人確認書類
•鍵一式
また、固定資産税や都市計画税は、引き渡し日を基準に日割り計算で精算されます。
ステップ7:確定申告
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、翌年の2月16日〜3月15日の間に確定申告を行う必要があります。譲渡所得には所得税と住民税が課税されますが、一定の条件を満たせば、3,000万円の特別控除などの特例を利用できる場合があります。
確定申告に必要な書類は、売却時の売買契約書、購入時の売買契約書、仲介手数料の領収書などです。税理士に相談することで、適切な節税対策を講じることができます。
不動産売却にかかる費用と税金
不動産売却には、以下のような費用と税金がかかります。事前に把握しておくことで、手取り額を正確に計算できます。
仲介手数料
不動産会社に支払う仲介手数料は、売却価格に応じて以下のように計算されます。
| 売却価格 | 仲介手数料の上限 |
| 200万円以下 | 売却価格の5% + 消費税 |
| 200万円超〜400万円以下 | 売却価格の4% + 2万円 + 消費税 |
| 400万円超 | 売却価格の3% + 6万円 + 消費税 |
例えば、3,000万円で売却した場合、仲介手数料は 105.6万円((3,000万円 × 3% + 6万円) × 1.1)となります。
印紙税
売買契約書に貼付する印紙代です。売却価格に応じて以下のように定められています。
| 売却価格 | 印紙税額 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 3万円 |
登録免許税
住宅ローンが残っている場合、抵当権を抹消するための登録免許税がかかります。費用は、不動産1件につき1,000円です。
譲渡所得税・住民税
不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得税と住民税が課税されます。税率は、所有期間によって異なります。
| 所有期間 | 所得税 | 住民税 | 合計 |
| 5年以下(短期譲渡所得) | 30% | 9% | 39% |
| 5年超(長期譲渡所得) | 15% | 5% | 20% |
ただし、居住用財産の3,000万円特別控除を利用できれば、譲渡所得から最大3,000万円を控除できるため、多くのケースで税金を大幅に軽減できます。
【重要】あなたの物件、実は「京町家」かもしれません
ここまで、一般的な不動産売却の流れと相場について解説してきましたが、京都市内の物件を売却される方に、ぜひ知っていただきたい重要なポイントがあります。
それは、あなたの物件が「京町家」に該当する可能性があるということです。

京町家とは?
京町家とは、主に1950年以前に建てられた、伝統的な木造軸組工法の住宅を指します。格子戸、通り庭、坪庭、虫籠窓(むしこまど)といった特徴的な意匠を持ち、京都の景観を形成する重要な文化的資産です。
なぜ「町家」だと分かることが重要なのか?
一般的な中古住宅として売却しようとすると、「古い」「使いづらい」といったマイナス面ばかりが強調され、適正な価格で売れない可能性があります。しかし、町家は希少性が高く、国内外から高い需要があるため、専門知識を持つ不動産会社に相談することで、より高値で売却できる可能性があります。
あなたの家が町家かどうかを見分ける5つのチェックリスト
以下の項目に複数当てはまる場合、あなたの物件は「京町家」である可能性が高いです。
1.建築年: 1950年(昭和25年)以前に建てられた
2.構造: 伝統的な木造軸組工法(柱と梁で支える構造)
3.意匠: 格子戸、通り庭、坪庭、虫籠窓などがある
4.立地: 京都市中心部、旧街道沿い、歴史的な町並みの中にある
5.間取り: 「うなぎの寝床」と呼ばれる奥行きの長い敷地
もし、これらの特徴に心当たりがある場合は、一般的な不動産会社ではなく、町家・古民家の専門知識を持つ不動産会社に相談することを強くおすすめします。
町家専門の不動産会社に相談するメリット
•町家の文化的・歴史的価値を正しく評価してもらえる
•町家を求める買主(投資家、事業者、海外からの購入者など)とのネットワークがある
•再建築不可物件や、接道義務を満たさない物件でも、適切な売却方法を提案してもらえる
•京都市の補助金制度や条例に精通しており、売却前の修繕や活用方法についてもアドバイスを受けられる
京都市の不動産売却で失敗しないための3つの注意点
1. 複数の不動産会社に査定を依頼する
1社だけの査定では、その価格が適正かどうか判断できません。最低でも3社以上に査定を依頼し、査定額だけでなく、その根拠や販売戦略についても説明を受けましょう。
特に、築古物件や町家の場合は、専門性の有無が査定額に大きく影響します。
2. 「再建築不可」物件かどうかを確認する
京都市内には、接道義務を満たさない、または建築基準法上の道路に接していないため、「再建築不可」となる物件が多く存在します。このような物件は、一般的な不動産会社では扱いにくいため、専門業者に相談することが重要です。
3. 売却のタイミングを見極める
2025年の京都市の不動産市場は横ばいで推移すると予測されていますが、空き家のまま放置すると、固定資産税の負担増や建物の劣化が進むリスクがあります。「いつか売ろう」と先延ばしにせず、早めに行動することが、結果的に有利な売却につながります。

まとめ
京都市の不動産売却は、相場の把握、適切な不動産会社の選定、そして物件の特性(特に町家かどうか)を正しく理解することが成功の鍵です。
2025年の市場は安定しており、売却しやすい環境が続いていますが、専門知識を持つパートナーを選ぶことで、より満足のいく結果を得ることができます。
もし、あなたの物件が町家に該当する可能性がある場合は、一般的な不動産会社だけでなく、町家・古民家の専門家にも相談してみることをおすすめします。適切なアドバイスを受けることで、思わぬ高値での売却や、売却以外の活用方法が見つかるかもしれません。